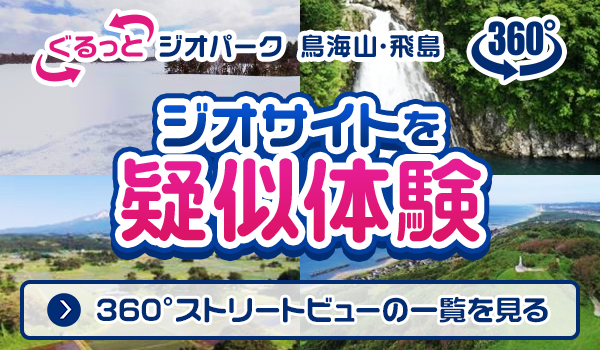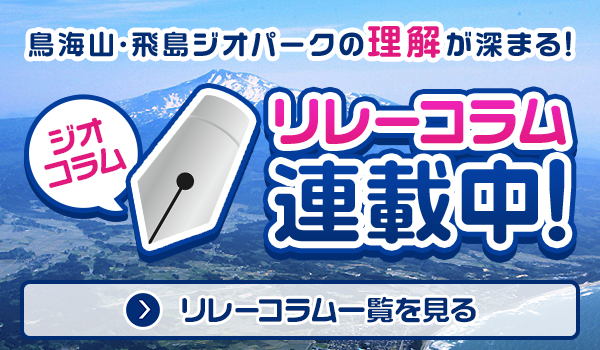観光地一覧
観光地一覧
全て
地質サイト
自然サイト
文化サイト
ビューポイント
施設

- 新山溶岩ドームと火山弾
- 1801(享和元)年の噴火でできた新山溶岩ドームは直径300m、比高は70mあります。この噴火でできた新山(別名享和岳)の体積は90万㎥、火山灰も含む全体の噴出量は約102万5千㎥と推定されています。...

- 鳥海山山腹の正断層群
- 日本列島には数多くの断層がありますが、動く方向によって正断層、逆断層、横ずれ断層と分類されています。東北地方に見られる断層は主に逆断層です。正断層は日本でも九州に行かなければなかなか目にすることができ...

- 白井新田の学田と堰
- 庄内藩の郡代であった白井矢太夫の藩校致道館の学田構想に基づき、1800年より開発された農地です。 鳥海山の冷たい湧水を温めるために水路を何度も迂回させたり、防風樹を植栽するなど数々の知恵がみられます...

- 白井新田の湿地群
- 湿地帯に生息する日本一小さなトンボであるハッチョウトンボの群生地。体長は約2cm で、オスは成熟すると鮮やかな赤色になります。山形県の準絶滅危惧種・遊佐町天然記念物に指定されており、地域では「ハッチョ...

- 遊佐元町湧水(自噴井)群
- 遊佐町の中心部の元町地区は鳥海山から流れてくる月光川の本流が山地を抜けて庄内平野に出るところに広がる扇状地の上にあります。そのため地下水が非常に豊富で水圧も高く、井戸を掘ればだいたいどこでも地面より高...

- 十六羅漢岩
- およそ10万年前に流れ出て溶岩にいくつもの羅漢像が彫られています。明治の初め、吹浦海禅寺の第21代寛海和尚が、海難事故でなくなった漁師たちの供養と海上安全を願って彫ったものだと伝わっています。

- 三崎海岸
- 今からおよそ3,000年前に鳥海山の猿穴(直径約50mの火口)付近から西側に流れ出した安山岩の溶岩流が、小砂川と女鹿の間の海岸まで達してできた海岸です。 溶岩流は海岸付近では60m以上の厚さがあり、...

- 釜磯
- 鳥海山は約60万年前からの火山活動によって流れた溶岩が重なりあってできていて、釜磯海岸も鳥海山から海中まで流れ込んだ溶岩でできています。 冷えて固まった溶岩の上部と下部はガサガサの溶岩で、これがスポ...

- 胴腹滝
- 今からおよそ16万年から2万年前に鳥海湖付近から噴き出した溶岩の末端崖から2筋の滝が流れ出しています。 渓流が滝になっているのではなく、標高230mの山腹の中から湧き出していて、身体の「どうっぱら」...

- 鳥海湖
- 鉾立の登山口からおよそ2時間の鳥海山7合目御浜神社付近より南側に展望することができます。湖面の海抜は約1600mで、南北にやや長い楕円形で直径約200mの火口湖です。 約16万年前の火山活動の時の火...
御田ヶ原の流土階段(全景).jpg)
- 鳥海山の周氷河地形
- 鳥海山のような寒冷地で、冬に強風で雪も飛ばされ地表があらわになり、大地に含まれる水分が凍ったり融けたりすることを繰り返すことによっておこる諸現象を「周氷河現象」といいます。 水は氷になると体積が増え...

- 庄内平野東縁断層帯
- 国道345号線沿いの庄内平野と出羽山地の境目には、長さ約38㎞にわたってほぼ南北方向に延びる直線的な急崖があります。この急崖は庄内平野東縁断層帯と呼ばれる活断層の動きがつくった崖です。 活断層が引き...

- 八ツ面川(イバラトミヨ生息地)
- イバラトミヨはトゲウオ科トミヨ属の魚です。遊佐の街中を流れる八ツ面川は、周辺の自噴井からの水が流れ込み、夏でも低い水温を維持できるため、氷河期の遺存種であるイバラトミヨが生息しています。かつて家庭雑排...

- 神泉の水
- 「神子の水」は遊佐町の女鹿集落にある湧き水を利用した洗い場です。原泉は集落の東側の山にあり、「神泉の水」は湧水を山の神より普請して引いてきたことからこの名がついたと言われています。 洗い場は利用用途...

- 鳥海山大物忌神社 (吹浦口ノ宮)
- 出羽国一ノ宮である鳥海山大物忌神社の起源は大変古く、昭和38年(1963)に1400年祭が執り行われたことから庄内地方では最古の歴史を持つ神社ではないかといわれています。本社は鳥海山の山頂に鎮座し、麓...

- 鳥海山大物忌神社 (蕨岡口ノ宮)
- 出羽国一ノ宮である鳥海山大物忌神社の起源は大変古く、昭和38年(1963)に1400年祭が執り行われたことから庄内地方では最古の歴史を持つ神社ではないかといわれています。本社は鳥海山の山頂に鎮座し、麓...

- 庄内砂丘
- 川から運ばれてきた砂が、大陸からの季節風と波によって陸側に吹き飛ばされてできた砂丘で、南北約35㎞に及びます。約8000年前から成長を始めたこの砂丘では、飛砂を防ぐために、江戸時代(17世紀)からクロ...

- 高瀬峡と大滝
- 高瀬峡は、鳥海山の南麓標高約350mに位置する峡谷です。このあたりの地形は約10万年前に鳥海山から流れ出た溶岩がつくったもので、鳥海山に由来する清流とともに豊かな自然美を作り出しています。駐車場や散策...

- 鳥海温泉 遊楽里
- 鳥海山と日本海を眺める宿泊施設。館内の展示ホールはジオパークのインフォメーションセンターになっています。 鳥海温泉 遊楽里のストリートビューを見る...

- 新山溶岩ドームと火山弾
- 1801(享和元)年の噴火でできた新山溶岩ドームは直径300m、比高は70mあります。この噴火でできた新山(別名享和岳)の体積は90万㎥、火山灰も含む全体の噴出量は約102万5千㎥と推定されています。...

- 鳥海山山腹の正断層群
- 日本列島には数多くの断層がありますが、動く方向によって正断層、逆断層、横ずれ断層と分類されています。東北地方に見られる断層は主に逆断層です。正断層は日本でも九州に行かなければなかなか目にすることができ...

- 遊佐元町湧水(自噴井)群
- 遊佐町の中心部の元町地区は鳥海山から流れてくる月光川の本流が山地を抜けて庄内平野に出るところに広がる扇状地の上にあります。そのため地下水が非常に豊富で水圧も高く、井戸を掘ればだいたいどこでも地面より高...

- 三崎海岸
- 今からおよそ3,000年前に鳥海山の猿穴(直径約50mの火口)付近から西側に流れ出した安山岩の溶岩流が、小砂川と女鹿の間の海岸まで達してできた海岸です。 溶岩流は海岸付近では60m以上の厚さがあり、...

- 釜磯
- 鳥海山は約60万年前からの火山活動によって流れた溶岩が重なりあってできていて、釜磯海岸も鳥海山から海中まで流れ込んだ溶岩でできています。 冷えて固まった溶岩の上部と下部はガサガサの溶岩で、これがスポ...

- 胴腹滝
- 今からおよそ16万年から2万年前に鳥海湖付近から噴き出した溶岩の末端崖から2筋の滝が流れ出しています。 渓流が滝になっているのではなく、標高230mの山腹の中から湧き出していて、身体の「どうっぱら」...

- 鳥海湖
- 鉾立の登山口からおよそ2時間の鳥海山7合目御浜神社付近より南側に展望することができます。湖面の海抜は約1600mで、南北にやや長い楕円形で直径約200mの火口湖です。 約16万年前の火山活動の時の火...
御田ヶ原の流土階段(全景).jpg)
- 鳥海山の周氷河地形
- 鳥海山のような寒冷地で、冬に強風で雪も飛ばされ地表があらわになり、大地に含まれる水分が凍ったり融けたりすることを繰り返すことによっておこる諸現象を「周氷河現象」といいます。 水は氷になると体積が増え...

- 庄内平野東縁断層帯
- 国道345号線沿いの庄内平野と出羽山地の境目には、長さ約38㎞にわたってほぼ南北方向に延びる直線的な急崖があります。この急崖は庄内平野東縁断層帯と呼ばれる活断層の動きがつくった崖です。 活断層が引き...

- 白井新田の学田と堰
- 庄内藩の郡代であった白井矢太夫の藩校致道館の学田構想に基づき、1800年より開発された農地です。 鳥海山の冷たい湧水を温めるために水路を何度も迂回させたり、防風樹を植栽するなど数々の知恵がみられます...

- 十六羅漢岩
- およそ10万年前に流れ出て溶岩にいくつもの羅漢像が彫られています。明治の初め、吹浦海禅寺の第21代寛海和尚が、海難事故でなくなった漁師たちの供養と海上安全を願って彫ったものだと伝わっています。

- 神泉の水
- 「神子の水」は遊佐町の女鹿集落にある湧き水を利用した洗い場です。原泉は集落の東側の山にあり、「神泉の水」は湧水を山の神より普請して引いてきたことからこの名がついたと言われています。 洗い場は利用用途...

- 鳥海山大物忌神社 (吹浦口ノ宮)
- 出羽国一ノ宮である鳥海山大物忌神社の起源は大変古く、昭和38年(1963)に1400年祭が執り行われたことから庄内地方では最古の歴史を持つ神社ではないかといわれています。本社は鳥海山の山頂に鎮座し、麓...

- 鳥海山大物忌神社 (蕨岡口ノ宮)
- 出羽国一ノ宮である鳥海山大物忌神社の起源は大変古く、昭和38年(1963)に1400年祭が執り行われたことから庄内地方では最古の歴史を持つ神社ではないかといわれています。本社は鳥海山の山頂に鎮座し、麓...

- 庄内砂丘
- 川から運ばれてきた砂が、大陸からの季節風と波によって陸側に吹き飛ばされてできた砂丘で、南北約35㎞に及びます。約8000年前から成長を始めたこの砂丘では、飛砂を防ぐために、江戸時代(17世紀)からクロ...