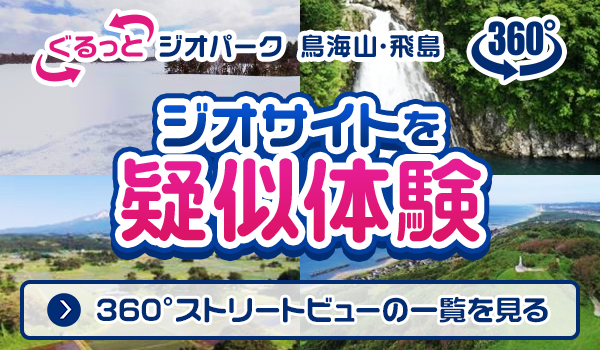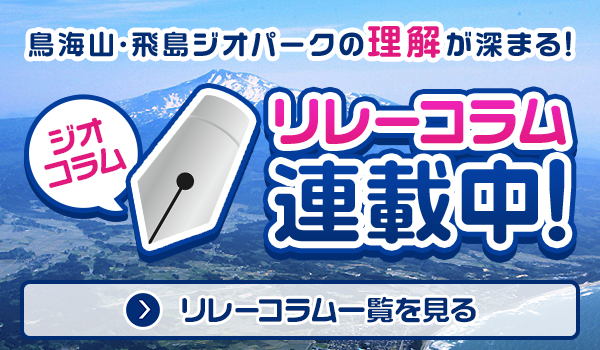※九十九島での再認定審査現地確認の様子
四季のある日本で暮らす私たちは、移ろいゆくものへの感受性が高いと言われています。無常、花鳥風月、侘び寂びの文化。そのようなアイデンティティが育まれた背景には、災害が多い日本ならではの土地柄があります。
日本では、身近な風景を一変させる災害が毎年のように発生しています。鳥海山・飛島ジオパークでも昨年の豪雨災害は記憶に新しいかと思います。もう少し昔を見てみると、鳥海山の火山活動と岩なだれ、1804年の象潟地震による九十九島の隆起など、地球の長い歴史からみるとごく短期間で、この地の景観は大きく変化してきました。その度に、ここで暮らす人たちは多くの犠牲を払い、困難に直面してきたわけです。
それでも、鳥海山や九十九島のダイナミックな変動と、そこで培われてきた知恵や工夫に触れた時、素直に美しいと思ってしまうのです。今、目の前にある九十九島に慈しみの気持ちを抱いてしまうのです。松尾芭蕉が訪れた時の九十九島は見られませんが、今見ているその景観も絶えず変わり続けていくのですから。
火山と地震が織りなす鳥海山・飛島ジオパークの暮らしは、自然と向き合い続ける私たちの美しさを凝縮した、世界に誇る遺産であると、個人的に思います。
※筆者の香取拓馬さんは、昨年行われた鳥海山・飛島ジオパークの再認定審査(現地調査)の調査員として構成自治体を訪問されました。