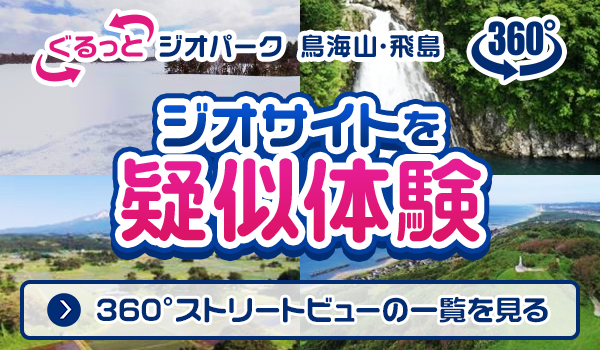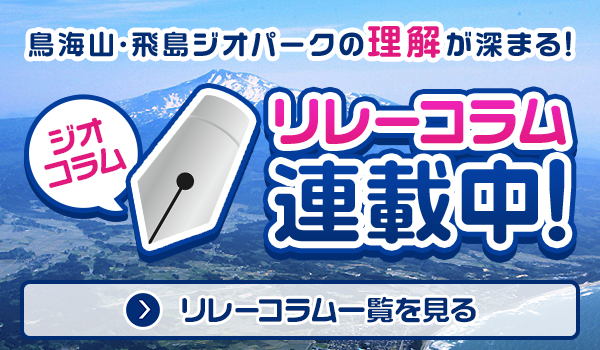にかほエリア
にかほエリア
全て
地質サイト
自然サイト
文化サイト
ビューポイント
施設

- 九十九島
- 秋田県にかほ市象潟(きさかた)には、水田の中にたくさんの丘が点在する独特の景色が広がります。「九十九島」(くじゅうくしま)と呼ばれるこれらの丘は、約2,500年前(紀元前466年)に発生した鳥海山の...

- 三崎海岸
- 今からおよそ3,000年前に鳥海山の猿穴(直径約50mの火口)付近から西側に流れ出した安山岩の溶岩流が、小砂川と女鹿の間の海岸まで達してできた海岸です。 溶岩流は海岸付近では60m以上の厚さがあり、...

- 院内油田跡地
- 院内油田はかつては国内有数の産油量を誇った油田です。 大正11年、大日本石油鉱業(株)が試掘を始めたのを皮切りに、急速な開発が進むことになりました。周辺には、院内・桂坂・小滝・上浜の四油田がありました...

- 仁賀保高原
- 鳥海山の岩なだれ堆積物がつくった標高約500mにある高原部です。爽やかな風を感じながら、広々とした牧草地や緑のなかに点在する湖沼、鳥海山を望むことができる場所です。

- 上郷の温水路群
- 稲作に利用していた鳥海山の冷水を温め、生育障害を解消するため、上郷地区の住民が考案して作った農業用水路です。水路の幅を広く、水深を浅くし、多くの落差を設けて空気と混ぜる構造で、昭和2年に日本で初めて作...

- 由利海岸波除石垣
- 江戸時代に日本海の波浪や強風による塩害から農地と農作物、海岸沿いを走る北国街道を守るために築かれた石垣です。表面は30~50cmの自然石・内部は砂利という構造や、水抜きの配置など、先人の知恵が随所に見...

- 唐戸石
- 「唐戸石」は今からおよそ2,500年前(紀元前466年)に発生した鳥海山の山体崩壊によって山頂付近から大量に流れてきた岩石の一つです。象潟海岸にたくさんある岩の中でも、ひときわ目立った大岩で、高さ4....

- 福田の泉
- 福田の泉は高さ50mほどの崖の下から出る湧き水です。この崖は約14万年前に鳥海山から流れ出た溶岩で、うすい板が積み重なったような板状節理(溶岩がゆっくり流れるときにできる板状の割れ目)が見られます。 ...

- 高森眺望台
- 旧仁賀保町市街地から由利原方面へ向かう県道32号線(仁賀保矢島館合線)の標高約230mに位置する眺望台です。 ここから西を望むと、象潟から仁賀保に至る平野と海岸線、日本海を一望することができます。 ...

- にかほ市観光拠点センター「にかほっと」
- にかほ市のおいしい産物が並ぶ店や無料の足湯が楽しめる複合施設。夏には鳥海山と日本海の恵み、近海で取れた「天然岩ガキ」を目当てに多くの人が訪れます。

- にかほ市象潟郷土資料館
- 九十九島(象潟)のなりたちや歴史・文化を分かりやすく知ることができる資料館。埋もれ木も展示しています。 にかほ市象潟郷土資料館の様子をストリートビューを見る...

- 奈曽の白滝と金峰神社
- 奈曽の白滝は落差26m・幅11mの名瀑で、滝をつくる岩盤は約10万年以前の鳥海山の溶岩と推定されます。鳥海山の修験の拠点であった金峰神社の境内をすすみ、長い石段を降りると、右手に神社社殿、左手に滝を見...

- 奈曽渓谷
- 奈曽渓谷は鳥海山の6合目付近から北側に伸びる深さ約300m~500m、幅約500m~1000mの渓谷です。展望台の真下は深さ337mのV字の形をしています。ここに東京タワーを持ってくると目の先にちょ...

- 冬師湿原
- にかほ市冬師地区にある冬師湿原です。このあたりには流れ山と呼ばれる小さな山の高まりと、その間の窪地にある小さな溜め池や湿原がたくさんあります。この地形は象潟の九十九島を作ったおよそ2500年前の鳥海...

- 象潟岩なだれ堆積物と埋もれ木
- およそ2500年前の紀元前466年に鳥海山の山体崩壊による岩なだれが発生し、約60億トンの土砂が流れ出しました。その岩なだれの土砂の下に木材が空気と触れることなく長い間地中に埋没していました。 ...

- 元滝伏流水
- 駐車場から約750m歩くと、「元滝伏流水」に到着します。「元滝伏流水」は、鳥海山の溶岩の末端崖から溢れ出す湧水がつくる滝です。滝の大きさは落差約5m、幅約30mで、湧き出す水の水温は一年を通してほぼ...

- 中島台・獅子ヶ鼻湿原
- 「中島台」は、厳しい自然の中を生き抜いてきたブナやミズナラの巨木が群生する森で、散策コースは一周約5kmでほとんど木道になっています。木道を歩いているといろいろな形をしているブナの木が見つかり、林野庁...

- 九十九島
- 秋田県にかほ市象潟(きさかた)には、水田の中にたくさんの丘が点在する独特の景色が広がります。「九十九島」(くじゅうくしま)と呼ばれるこれらの丘は、約2,500年前(紀元前466年)に発生した鳥海山の...

- 三崎海岸
- 今からおよそ3,000年前に鳥海山の猿穴(直径約50mの火口)付近から西側に流れ出した安山岩の溶岩流が、小砂川と女鹿の間の海岸まで達してできた海岸です。 溶岩流は海岸付近では60m以上の厚さがあり、...

- 奈曽の白滝と金峰神社
- 奈曽の白滝は落差26m・幅11mの名瀑で、滝をつくる岩盤は約10万年以前の鳥海山の溶岩と推定されます。鳥海山の修験の拠点であった金峰神社の境内をすすみ、長い石段を降りると、右手に神社社殿、左手に滝を見...

- 奈曽渓谷
- 奈曽渓谷は鳥海山の6合目付近から北側に伸びる深さ約300m~500m、幅約500m~1000mの渓谷です。展望台の真下は深さ337mのV字の形をしています。ここに東京タワーを持ってくると目の先にちょ...

- 冬師湿原
- にかほ市冬師地区にある冬師湿原です。このあたりには流れ山と呼ばれる小さな山の高まりと、その間の窪地にある小さな溜め池や湿原がたくさんあります。この地形は象潟の九十九島を作ったおよそ2500年前の鳥海...

- 象潟岩なだれ堆積物と埋もれ木
- およそ2500年前の紀元前466年に鳥海山の山体崩壊による岩なだれが発生し、約60億トンの土砂が流れ出しました。その岩なだれの土砂の下に木材が空気と触れることなく長い間地中に埋没していました。 ...

- 元滝伏流水
- 駐車場から約750m歩くと、「元滝伏流水」に到着します。「元滝伏流水」は、鳥海山の溶岩の末端崖から溢れ出す湧水がつくる滝です。滝の大きさは落差約5m、幅約30mで、湧き出す水の水温は一年を通してほぼ...

- 中島台・獅子ヶ鼻湿原
- 「中島台」は、厳しい自然の中を生き抜いてきたブナやミズナラの巨木が群生する森で、散策コースは一周約5kmでほとんど木道になっています。木道を歩いているといろいろな形をしているブナの木が見つかり、林野庁...

- 院内油田跡地
- 院内油田はかつては国内有数の産油量を誇った油田です。 大正11年、大日本石油鉱業(株)が試掘を始めたのを皮切りに、急速な開発が進むことになりました。周辺には、院内・桂坂・小滝・上浜の四油田がありました...

- 仁賀保高原
- 鳥海山の岩なだれ堆積物がつくった標高約500mにある高原部です。爽やかな風を感じながら、広々とした牧草地や緑のなかに点在する湖沼、鳥海山を望むことができる場所です。

- 上郷の温水路群
- 稲作に利用していた鳥海山の冷水を温め、生育障害を解消するため、上郷地区の住民が考案して作った農業用水路です。水路の幅を広く、水深を浅くし、多くの落差を設けて空気と混ぜる構造で、昭和2年に日本で初めて作...

- 由利海岸波除石垣
- 江戸時代に日本海の波浪や強風による塩害から農地と農作物、海岸沿いを走る北国街道を守るために築かれた石垣です。表面は30~50cmの自然石・内部は砂利という構造や、水抜きの配置など、先人の知恵が随所に見...

- 唐戸石
- 「唐戸石」は今からおよそ2,500年前(紀元前466年)に発生した鳥海山の山体崩壊によって山頂付近から大量に流れてきた岩石の一つです。象潟海岸にたくさんある岩の中でも、ひときわ目立った大岩で、高さ4....

- 福田の泉
- 福田の泉は高さ50mほどの崖の下から出る湧き水です。この崖は約14万年前に鳥海山から流れ出た溶岩で、うすい板が積み重なったような板状節理(溶岩がゆっくり流れるときにできる板状の割れ目)が見られます。 ...

- 奈曽の白滝と金峰神社
- 奈曽の白滝は落差26m・幅11mの名瀑で、滝をつくる岩盤は約10万年以前の鳥海山の溶岩と推定されます。鳥海山の修験の拠点であった金峰神社の境内をすすみ、長い石段を降りると、右手に神社社殿、左手に滝を見...