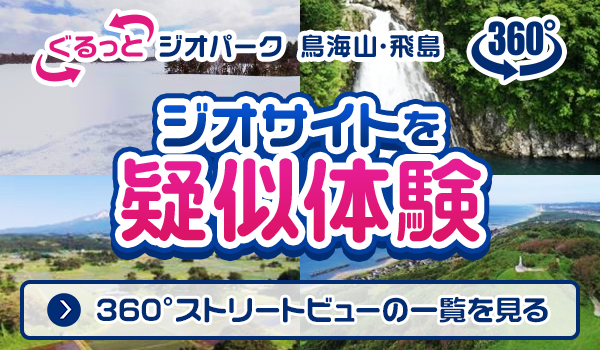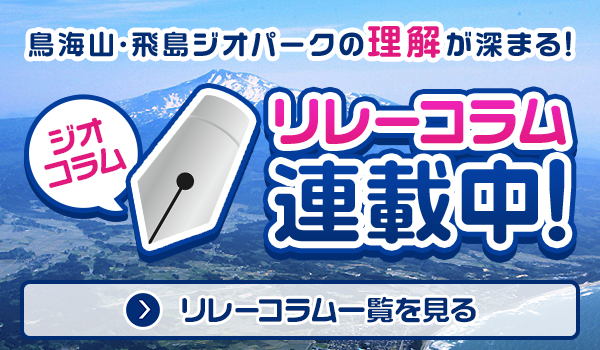地質サイト
地質サイト
全て
由利本荘エリア
にかほエリア
遊佐エリア
酒田エリア
飛島エリア

- 新山溶岩ドームと火山弾
- 1801(享和元)年の噴火でできた新山溶岩ドームは直径300m、比高は70mあります。この噴火でできた新山(別名享和岳)の体積は90万㎥、火山灰も含む全体の噴出量は約102万5千㎥と推定されています。...

- 鳥海山山腹の正断層群
- 日本列島には数多くの断層がありますが、動く方向によって正断層、逆断層、横ずれ断層と分類されています。東北地方に見られる断層は主に逆断層です。正断層は日本でも九州に行かなければなかなか目にすることができ...

- 二ノ滝(一ノ滝、二ノ滝渓谷)
- 二ノ滝は鳥海山の南麓の標高約500mに位置していますが、ここは今から約10万年前に噴火の時に流れ出した硬い安山岩の溶岩でできています。そこを鳥海山の豊富な水が削ってできた落差約20mの二筋の滝が流れて...

- 九十九島
- 秋田県にかほ市象潟(きさかた)には、水田の中にたくさんの丘が点在する独特の景色が広がります。「九十九島」(くじゅうくしま)と呼ばれるこれらの丘は、約2,500年前(紀元前466年)に発生した鳥海山の...

- 宮沢林道の大しゅう曲露頭
- 300万年前から日本列島にはプレートの動きにより東西方向から押される力が働きます。東日本全体が隆起し、しわが寄るように奥羽山脈や出羽丘陵ができ始めます。その力はとても大きく、地層が強い力を受けて押し曲...

- 遊佐元町湧水(自噴井)群
- 遊佐町の中心部の元町地区は鳥海山から流れてくる月光川の本流が山地を抜けて庄内平野に出るところに広がる扇状地の上にあります。そのため地下水が非常に豊富で水圧も高く、井戸を掘ればだいたいどこでも地面より高...

- 法体の滝とポットホール(甌穴)
- 約10万年前の鳥海山の噴火で大量の溶岩が流れ出しました。その上を流れてきた子吉川の水が一気に溶岩の末端崖を流れ落ちることによって、落差約57mの美しい滝をつくりだしました。滝は三段になっていて、三の...

- 竜ヶ原湿原
- 鳥海山の祓川登山口に位置し、標高1170mにある東西約400m、南北約300mの広さの*高層湿原です。約2万年前に鳥海山が噴火したときに流れ出た七高山溶岩の末端部から湧き出している水が、約40万年前...

- 三崎海岸
- 今からおよそ3,000年前に鳥海山の猿穴(直径約50mの火口)付近から西側に流れ出した安山岩の溶岩流が、小砂川と女鹿の間の海岸まで達してできた海岸です。 溶岩流は海岸付近では60m以上の厚さがあり、...

- 釜磯
- 鳥海山は約60万年前からの火山活動によって流れた溶岩が重なりあってできていて、釜磯海岸も鳥海山から海中まで流れ込んだ溶岩でできています。 冷えて固まった溶岩の上部と下部はガサガサの溶岩で、これがスポ...

- 胴腹滝
- 今からおよそ16万年から2万年前に鳥海湖付近から噴き出した溶岩の末端崖から2筋の滝が流れ出しています。 渓流が滝になっているのではなく、標高230mの山腹の中から湧き出していて、身体の「どうっぱら」...

- 鳥海湖
- 鉾立の登山口からおよそ2時間の鳥海山7合目御浜神社付近より南側に展望することができます。湖面の海抜は約1600mで、南北にやや長い楕円形で直径約200mの火口湖です。 約16万年前の火山活動の時の火...
御田ヶ原の流土階段(全景).jpg)
- 鳥海山の周氷河地形
- 鳥海山のような寒冷地で、冬に強風で雪も飛ばされ地表があらわになり、大地に含まれる水分が凍ったり融けたりすることを繰り返すことによっておこる諸現象を「周氷河現象」といいます。 水は氷になると体積が増え...

- 庄内平野東縁断層帯
- 国道345号線沿いの庄内平野と出羽山地の境目には、長さ約38㎞にわたってほぼ南北方向に延びる直線的な急崖があります。この急崖は庄内平野東縁断層帯と呼ばれる活断層の動きがつくった崖です。 活断層が引き...

- 貝形雪渓
- 新庄市の方向(山の南側)から眺めると、まるで二枚貝のように見えることが、この雪渓の呼び名の由来です。標高約1400mのところにある貝形雪渓は、鳥海山の噴火で流れ出した複数の溶岩流に挟まれて出来た窪地に...

- 鶴間池
- 県道368号線の道沿いの展望スポット(地元で「のぞき」と呼ぶ)に行くと、鶴間池全体と周辺の地形が一望できます。標高約815mの場所にある鶴間池は、水深が3.9mとそれほど深くはありませんが、湧水がたま...

- 玉簾の滝
- 落差63mの玉簾の滝は出羽丘陵の一角にあります。北西を向いているので太陽高度や日差しによっては滝の飛沫が玉簾のように見える時があります。 出羽丘陵は1500万年ほど前にはまだ海の底にありました。その...

- 不動の滝
- 黒川地区の御瀧神社の背後に位置する落差約20mの不動の滝は、切り立った崖の上から水が流れ落ち、流量も豊富で一年中流れが絶えることがありません。 不動の滝の周辺の地層は約60万年前の鳥海火山のステージ...

- 十二滝
- 水汲み滝、南滝、九の滝、てんつき滝、抱き帰りの滝、天狗滝、火揚滝、芯の滝、白紙垂の滝、蛇の滝、河原滝、合格滝の12の滝が、変化に富んだ美しい表情を見せてくれ、飽海三名瀑に数えられています。名前は十二支...

- 中野俣 金剛蔵
- 金剛蔵の100mを超す雄大な縞模様を見せてくれる露頭は地域の方から「平田のグランドキャニオン」と称されています。 今から約1500万年前にこのあたりがまだ深い海の底だったころに泥が堆積してできた地層...

- ゴトロ浜
- 南灯台のある崖は高さが20mあり、直径が5~10cmの緑色の丸い石を含む地層と火山灰の地層が交互に積み重なった互層になっています。これはおよそ1650万年前から900万年の間に、海底の火山活動で噴火が...

- 烏帽子群島
- 飛島の西方約1kmにある烏帽子群島は、日本海が広がってきたころに海底火山の活動によって噴出した溶岩が、ゆっくりと冷えて固まるときにできる柱のような節理の柱状節理がたくさん見られる島々です。岩が黒っぽく...

- 御積島
- 御積島は飛島の西方約1kmに位置し、飛島本島よりも高い標高72mあります。日本海が拡大したころの海底での火山活動による流紋岩でできていて、それが隆起してできた島です。 鳥海国定公園の特別保護地区に指...

- 荒崎海岸
- 飛島は日本海が広がってきたころに海底火山から噴き出した噴出物が海底に積み重なり、それが隆起してできた島ですが、荒崎海岸はその噴火の時の軽石や流紋岩の破片を含んだ火山礫凝灰岩でできています。 荒崎周辺...

- 飛島の津波堆積物
- 飛島の西側や北側の法木地区の隆起ベンチを覆っている緩斜面に、有機質の土壌層の中に礫の層が挟まれているところが何か所か見つかります。その露頭は標高5~8mの高さで、堆積物の厚さは合計で1m程度です。 ...

- 八幡崎
- 八幡崎は飛島の北端に突き出た崖で、海底火山の活動による火山灰が堆積したものです。 周りには「ゴジラのしっぽ」や「龍の背」と呼ばれている「岩脈」がたくさん見つかりますが、この岩脈をそれぞれたどっていくと...

- 二俣島
- 二俣島は島全体が玄武岩の「柱状節理」でできています。 日本が大陸から分かれてきて日本海ができたころに、海底火山の活動でできたと考えられていますが日本海が広く大きくなってくる中で、海底火山の活動がたい...

- 奈曽の白滝と金峰神社
- 奈曽の白滝は落差26m・幅11mの名瀑で、滝をつくる岩盤は約10万年以前の鳥海山の溶岩と推定されます。鳥海山の修験の拠点であった金峰神社の境内をすすみ、長い石段を降りると、右手に神社社殿、左手に滝を見...

- 牛渡川と丸池様
- 牛渡川は鳥海山の溶岩の縁に沿って流れる全長4kmあまりの小さな川ですが、川の水のほぼ100%が岩の割れ目や石と石の間から湧き出す湧き水です。その流量は24t/分あります。 水温は年間を通してほぼ11...

- 亀田不動滝
- 標高約150mのところにある亀田不動滝は、落差約25m、幅約10mの溶岩に白布を垂らしたように流れる勇壮な滝で、流量も豊富で一年中流れが絶えることがありません。ここの岩は粗粒玄武岩(ドレライト)です...

- 赤田大滝
- 落差23mの滝で、滝上部のところで流れを変えています。滝の上部に見える白っぽい岩は今から2300万年前~533万年ころに海底火山が噴火してできた流紋岩です。このあたりの地質がとても複雑に細かいエリア...

- 新山公園(新山安山岩)
- 今から約800万年前、この辺りがまだ浅い海の中だったころに海底火山が噴火し、火山灰、火山礫、火山岩塊が堆積しました。火山活動で放出されたさまざまな大きさの砕屑物が固まってできた岩石を火砕岩といいますが...

- 石沢大滝と屏風岩
- 今から3000万年ほど前はまだ日本海もなく、このあたりはユーラシア大陸の東端にありました。その当時の陸上での火山の噴火で噴出した溶岩が冷えて安山岩になり、現在地表で見られるだけでも500m以上堆積し...

- 奈曽渓谷
- 奈曽渓谷は鳥海山の6合目付近から北側に伸びる深さ約300m~500m、幅約500m~1000mの渓谷です。展望台の真下は深さ337mのV字の形をしています。ここに東京タワーを持ってくると目の先にちょ...

- 冬師湿原
- にかほ市冬師地区にある冬師湿原です。このあたりには流れ山と呼ばれる小さな山の高まりと、その間の窪地にある小さな溜め池や湿原がたくさんあります。この地形は象潟の九十九島を作ったおよそ2500年前の鳥海...

- 象潟岩なだれ堆積物と埋もれ木
- およそ2500年前の紀元前466年に鳥海山の山体崩壊による岩なだれが発生し、約60億トンの土砂が流れ出しました。その岩なだれの土砂の下に木材が空気と触れることなく長い間地中に埋没していました。 ...

- 檜山滝
- 沢内沢川上流部に位置し、柱状節理が階段状に発達した上を流れる滝で推定落差は50mです。泥岩が堆積していた地層の中に地表近くまでデイサイトが貫入してきましたが、大部分は噴出しないでそのままゆっくりと冷...

- 元滝伏流水
- 駐車場から約750m歩くと、「元滝伏流水」に到着します。「元滝伏流水」は、鳥海山の溶岩の末端崖から溢れ出す湧水がつくる滝です。滝の大きさは落差約5m、幅約30mで、湧き出す水の水温は一年を通してほぼ...

- 柏木山と海岸遊歩道
- 柏木山、百合島、舘岩は赤っぽい色をしていて、約900万年前に噴き出した粘り気の強い溶岩が固まった流紋岩でできています。 島の南端から賽の河原にかけては、溶岩が固まるときに流れたきれいな流理構造の見ら...

- 中島台・獅子ヶ鼻湿原
- 「中島台」は、厳しい自然の中を生き抜いてきたブナやミズナラの巨木が群生する森で、散策コースは一周約5kmでほとんど木道になっています。木道を歩いているといろいろな形をしているブナの木が見つかり、林野庁...

- ボツメキ湧水
- 標高713mの八塩山(やしおさん)の東側の急な斜面からゆるい斜面に変わるところにある湧水です。八塩山の北側や西側には谷が発達していますが、東縁には八塩山断層が発達し、西側や北側に比べると雨や雪どけ水...

- 宮沢林道の大しゅう曲露頭
- 300万年前から日本列島にはプレートの動きにより東西方向から押される力が働きます。東日本全体が隆起し、しわが寄るように奥羽山脈や出羽丘陵ができ始めます。その力はとても大きく、地層が強い力を受けて押し曲...

- 法体の滝とポットホール(甌穴)
- 約10万年前の鳥海山の噴火で大量の溶岩が流れ出しました。その上を流れてきた子吉川の水が一気に溶岩の末端崖を流れ落ちることによって、落差約57mの美しい滝をつくりだしました。滝は三段になっていて、三の...

- 竜ヶ原湿原
- 鳥海山の祓川登山口に位置し、標高1170mにある東西約400m、南北約300mの広さの*高層湿原です。約2万年前に鳥海山が噴火したときに流れ出た七高山溶岩の末端部から湧き出している水が、約40万年前...

- 亀田不動滝
- 標高約150mのところにある亀田不動滝は、落差約25m、幅約10mの溶岩に白布を垂らしたように流れる勇壮な滝で、流量も豊富で一年中流れが絶えることがありません。ここの岩は粗粒玄武岩(ドレライト)です...

- 赤田大滝
- 落差23mの滝で、滝上部のところで流れを変えています。滝の上部に見える白っぽい岩は今から2300万年前~533万年ころに海底火山が噴火してできた流紋岩です。このあたりの地質がとても複雑に細かいエリア...

- 新山公園(新山安山岩)
- 今から約800万年前、この辺りがまだ浅い海の中だったころに海底火山が噴火し、火山灰、火山礫、火山岩塊が堆積しました。火山活動で放出されたさまざまな大きさの砕屑物が固まってできた岩石を火砕岩といいますが...

- 石沢大滝と屏風岩
- 今から3000万年ほど前はまだ日本海もなく、このあたりはユーラシア大陸の東端にありました。その当時の陸上での火山の噴火で噴出した溶岩が冷えて安山岩になり、現在地表で見られるだけでも500m以上堆積し...

- 檜山滝
- 沢内沢川上流部に位置し、柱状節理が階段状に発達した上を流れる滝で推定落差は50mです。泥岩が堆積していた地層の中に地表近くまでデイサイトが貫入してきましたが、大部分は噴出しないでそのままゆっくりと冷...

- ボツメキ湧水
- 標高713mの八塩山(やしおさん)の東側の急な斜面からゆるい斜面に変わるところにある湧水です。八塩山の北側や西側には谷が発達していますが、東縁には八塩山断層が発達し、西側や北側に比べると雨や雪どけ水...

- 九十九島
- 秋田県にかほ市象潟(きさかた)には、水田の中にたくさんの丘が点在する独特の景色が広がります。「九十九島」(くじゅうくしま)と呼ばれるこれらの丘は、約2,500年前(紀元前466年)に発生した鳥海山の...

- 三崎海岸
- 今からおよそ3,000年前に鳥海山の猿穴(直径約50mの火口)付近から西側に流れ出した安山岩の溶岩流が、小砂川と女鹿の間の海岸まで達してできた海岸です。 溶岩流は海岸付近では60m以上の厚さがあり、...

- 奈曽の白滝と金峰神社
- 奈曽の白滝は落差26m・幅11mの名瀑で、滝をつくる岩盤は約10万年以前の鳥海山の溶岩と推定されます。鳥海山の修験の拠点であった金峰神社の境内をすすみ、長い石段を降りると、右手に神社社殿、左手に滝を見...

- 奈曽渓谷
- 奈曽渓谷は鳥海山の6合目付近から北側に伸びる深さ約300m~500m、幅約500m~1000mの渓谷です。展望台の真下は深さ337mのV字の形をしています。ここに東京タワーを持ってくると目の先にちょ...

- 冬師湿原
- にかほ市冬師地区にある冬師湿原です。このあたりには流れ山と呼ばれる小さな山の高まりと、その間の窪地にある小さな溜め池や湿原がたくさんあります。この地形は象潟の九十九島を作ったおよそ2500年前の鳥海...

- 象潟岩なだれ堆積物と埋もれ木
- およそ2500年前の紀元前466年に鳥海山の山体崩壊による岩なだれが発生し、約60億トンの土砂が流れ出しました。その岩なだれの土砂の下に木材が空気と触れることなく長い間地中に埋没していました。 ...

- 元滝伏流水
- 駐車場から約750m歩くと、「元滝伏流水」に到着します。「元滝伏流水」は、鳥海山の溶岩の末端崖から溢れ出す湧水がつくる滝です。滝の大きさは落差約5m、幅約30mで、湧き出す水の水温は一年を通してほぼ...

- 中島台・獅子ヶ鼻湿原
- 「中島台」は、厳しい自然の中を生き抜いてきたブナやミズナラの巨木が群生する森で、散策コースは一周約5kmでほとんど木道になっています。木道を歩いているといろいろな形をしているブナの木が見つかり、林野庁...

- 新山溶岩ドームと火山弾
- 1801(享和元)年の噴火でできた新山溶岩ドームは直径300m、比高は70mあります。この噴火でできた新山(別名享和岳)の体積は90万㎥、火山灰も含む全体の噴出量は約102万5千㎥と推定されています。...

- 鳥海山山腹の正断層群
- 日本列島には数多くの断層がありますが、動く方向によって正断層、逆断層、横ずれ断層と分類されています。東北地方に見られる断層は主に逆断層です。正断層は日本でも九州に行かなければなかなか目にすることができ...

- 二ノ滝(一ノ滝、二ノ滝渓谷)
- 二ノ滝は鳥海山の南麓の標高約500mに位置していますが、ここは今から約10万年前に噴火の時に流れ出した硬い安山岩の溶岩でできています。そこを鳥海山の豊富な水が削ってできた落差約20mの二筋の滝が流れて...

- 遊佐元町湧水(自噴井)群
- 遊佐町の中心部の元町地区は鳥海山から流れてくる月光川の本流が山地を抜けて庄内平野に出るところに広がる扇状地の上にあります。そのため地下水が非常に豊富で水圧も高く、井戸を掘ればだいたいどこでも地面より高...

- 三崎海岸
- 今からおよそ3,000年前に鳥海山の猿穴(直径約50mの火口)付近から西側に流れ出した安山岩の溶岩流が、小砂川と女鹿の間の海岸まで達してできた海岸です。 溶岩流は海岸付近では60m以上の厚さがあり、...

- 釜磯
- 鳥海山は約60万年前からの火山活動によって流れた溶岩が重なりあってできていて、釜磯海岸も鳥海山から海中まで流れ込んだ溶岩でできています。 冷えて固まった溶岩の上部と下部はガサガサの溶岩で、これがスポ...

- 胴腹滝
- 今からおよそ16万年から2万年前に鳥海湖付近から噴き出した溶岩の末端崖から2筋の滝が流れ出しています。 渓流が滝になっているのではなく、標高230mの山腹の中から湧き出していて、身体の「どうっぱら」...

- 鳥海湖
- 鉾立の登山口からおよそ2時間の鳥海山7合目御浜神社付近より南側に展望することができます。湖面の海抜は約1600mで、南北にやや長い楕円形で直径約200mの火口湖です。 約16万年前の火山活動の時の火...
御田ヶ原の流土階段(全景).jpg)
- 鳥海山の周氷河地形
- 鳥海山のような寒冷地で、冬に強風で雪も飛ばされ地表があらわになり、大地に含まれる水分が凍ったり融けたりすることを繰り返すことによっておこる諸現象を「周氷河現象」といいます。 水は氷になると体積が増え...

- 庄内平野東縁断層帯
- 国道345号線沿いの庄内平野と出羽山地の境目には、長さ約38㎞にわたってほぼ南北方向に延びる直線的な急崖があります。この急崖は庄内平野東縁断層帯と呼ばれる活断層の動きがつくった崖です。 活断層が引き...

- 牛渡川と丸池様
- 牛渡川は鳥海山の溶岩の縁に沿って流れる全長4kmあまりの小さな川ですが、川の水のほぼ100%が岩の割れ目や石と石の間から湧き出す湧き水です。その流量は24t/分あります。 水温は年間を通してほぼ11...

- 庄内平野東縁断層帯
- 国道345号線沿いの庄内平野と出羽山地の境目には、長さ約38㎞にわたってほぼ南北方向に延びる直線的な急崖があります。この急崖は庄内平野東縁断層帯と呼ばれる活断層の動きがつくった崖です。 活断層が引き...

- 貝形雪渓
- 新庄市の方向(山の南側)から眺めると、まるで二枚貝のように見えることが、この雪渓の呼び名の由来です。標高約1400mのところにある貝形雪渓は、鳥海山の噴火で流れ出した複数の溶岩流に挟まれて出来た窪地に...

- 鶴間池
- 県道368号線の道沿いの展望スポット(地元で「のぞき」と呼ぶ)に行くと、鶴間池全体と周辺の地形が一望できます。標高約815mの場所にある鶴間池は、水深が3.9mとそれほど深くはありませんが、湧水がたま...

- 玉簾の滝
- 落差63mの玉簾の滝は出羽丘陵の一角にあります。北西を向いているので太陽高度や日差しによっては滝の飛沫が玉簾のように見える時があります。 出羽丘陵は1500万年ほど前にはまだ海の底にありました。その...

- 不動の滝
- 黒川地区の御瀧神社の背後に位置する落差約20mの不動の滝は、切り立った崖の上から水が流れ落ち、流量も豊富で一年中流れが絶えることがありません。 不動の滝の周辺の地層は約60万年前の鳥海火山のステージ...

- 十二滝
- 水汲み滝、南滝、九の滝、てんつき滝、抱き帰りの滝、天狗滝、火揚滝、芯の滝、白紙垂の滝、蛇の滝、河原滝、合格滝の12の滝が、変化に富んだ美しい表情を見せてくれ、飽海三名瀑に数えられています。名前は十二支...

- 中野俣 金剛蔵
- 金剛蔵の100mを超す雄大な縞模様を見せてくれる露頭は地域の方から「平田のグランドキャニオン」と称されています。 今から約1500万年前にこのあたりがまだ深い海の底だったころに泥が堆積してできた地層...

- ゴトロ浜
- 南灯台のある崖は高さが20mあり、直径が5~10cmの緑色の丸い石を含む地層と火山灰の地層が交互に積み重なった互層になっています。これはおよそ1650万年前から900万年の間に、海底の火山活動で噴火が...

- 烏帽子群島
- 飛島の西方約1kmにある烏帽子群島は、日本海が広がってきたころに海底火山の活動によって噴出した溶岩が、ゆっくりと冷えて固まるときにできる柱のような節理の柱状節理がたくさん見られる島々です。岩が黒っぽく...

- 御積島
- 御積島は飛島の西方約1kmに位置し、飛島本島よりも高い標高72mあります。日本海が拡大したころの海底での火山活動による流紋岩でできていて、それが隆起してできた島です。 鳥海国定公園の特別保護地区に指...

- 荒崎海岸
- 飛島は日本海が広がってきたころに海底火山から噴き出した噴出物が海底に積み重なり、それが隆起してできた島ですが、荒崎海岸はその噴火の時の軽石や流紋岩の破片を含んだ火山礫凝灰岩でできています。 荒崎周辺...

- 飛島の津波堆積物
- 飛島の西側や北側の法木地区の隆起ベンチを覆っている緩斜面に、有機質の土壌層の中に礫の層が挟まれているところが何か所か見つかります。その露頭は標高5~8mの高さで、堆積物の厚さは合計で1m程度です。 ...

- 八幡崎
- 八幡崎は飛島の北端に突き出た崖で、海底火山の活動による火山灰が堆積したものです。 周りには「ゴジラのしっぽ」や「龍の背」と呼ばれている「岩脈」がたくさん見つかりますが、この岩脈をそれぞれたどっていくと...

- 二俣島
- 二俣島は島全体が玄武岩の「柱状節理」でできています。 日本が大陸から分かれてきて日本海ができたころに、海底火山の活動でできたと考えられていますが日本海が広く大きくなってくる中で、海底火山の活動がたい...

- 柏木山と海岸遊歩道
- 柏木山、百合島、舘岩は赤っぽい色をしていて、約900万年前に噴き出した粘り気の強い溶岩が固まった流紋岩でできています。 島の南端から賽の河原にかけては、溶岩が固まるときに流れたきれいな流理構造の見ら...