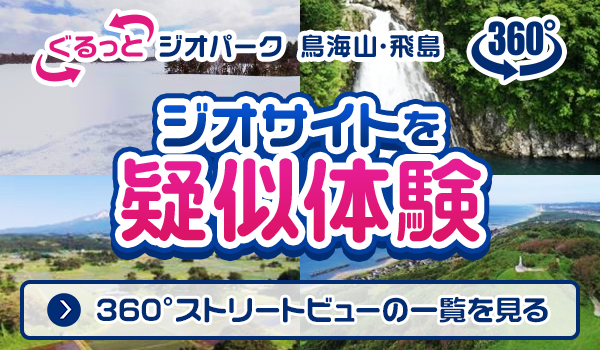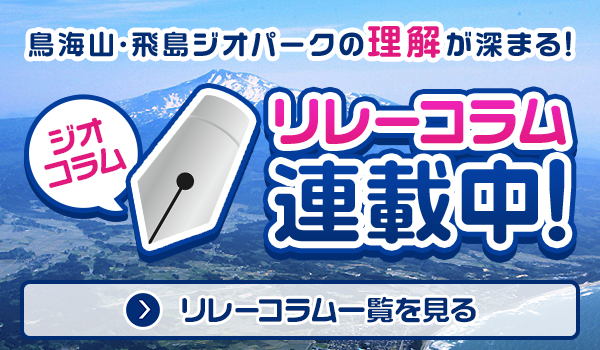文化サイト
文化サイト
全て
由利本荘エリア
にかほエリア
遊佐エリア
酒田エリア
飛島エリア

- 白井新田の学田と堰
- 庄内藩の郡代であった白井矢太夫の藩校致道館の学田構想に基づき、1800年より開発された農地です。 鳥海山の冷たい湧水を温めるために水路を何度も迂回させたり、防風樹を植栽するなど数々の知恵がみられます...

- 十六羅漢岩
- およそ10万年前に流れ出て溶岩にいくつもの羅漢像が彫られています。明治の初め、吹浦海禅寺の第21代寛海和尚が、海難事故でなくなった漁師たちの供養と海上安全を願って彫ったものだと伝わっています。

- 森子大物忌神社
- 鳥海山信仰における滝沢修験の拠点で秋田杉に囲まれた境内は、修験の聖地としての雰囲気に満ちています。 近年、毎年4月第3日曜日に行われている例大祭は、 米俵10俵分(約600kg)と言われる御輿を担ぎ...

- 由利原高原
- 鳥海山の巨大な岩なだれ堆積地が長い時間をかけてなだらかな地形が広がる高原になりました。広大な採草放牧地を活かして秋田由利牛やジャージー牛などが飼育されています。

- 由利原油ガス田
- 石油や天然ガスは、昔湖底や海底にたまった植物が長い時間をかけて分解されてできたものとされています。 かつて秋田県では、特定の時代の地層でしか石油は発掘されないといわれていましたが、由利原台地に油田・...

- 木境大物忌神社
- 木境大物忌神社は、鳥海山信仰の中心だった矢島の修験衆徒の活動拠点でした。 木境周辺では、大物忌神社を中心に春の入峰、虫除け祭り、秋の入峰などのさまざまな修行や行事が、一年を通じて行われていました。この...

- 院内油田跡地
- 院内油田はかつては国内有数の産油量を誇った油田です。 大正11年、大日本石油鉱業(株)が試掘を始めたのを皮切りに、急速な開発が進むことになりました。周辺には、院内・桂坂・小滝・上浜の四油田がありました...

- 仁賀保高原
- 鳥海山の岩なだれ堆積物がつくった標高約500mにある高原部です。爽やかな風を感じながら、広々とした牧草地や緑のなかに点在する湖沼、鳥海山を望むことができる場所です。

- 上郷の温水路群
- 稲作に利用していた鳥海山の冷水を温め、生育障害を解消するため、上郷地区の住民が考案して作った農業用水路です。水路の幅を広く、水深を浅くし、多くの落差を設けて空気と混ぜる構造で、昭和2年に日本で初めて作...

- 由利海岸波除石垣
- 江戸時代に日本海の波浪や強風による塩害から農地と農作物、海岸沿いを走る北国街道を守るために築かれた石垣です。表面は30~50cmの自然石・内部は砂利という構造や、水抜きの配置など、先人の知恵が随所に見...

- 唐戸石
- 「唐戸石」は今からおよそ2,500年前(紀元前466年)に発生した鳥海山の山体崩壊によって山頂付近から大量に流れてきた岩石の一つです。象潟海岸にたくさんある岩の中でも、ひときわ目立った大岩で、高さ4....

- 福田の泉
- 福田の泉は高さ50mほどの崖の下から出る湧き水です。この崖は約14万年前に鳥海山から流れ出た溶岩で、うすい板が積み重なったような板状節理(溶岩がゆっくり流れるときにできる板状の割れ目)が見られます。 ...

- 神泉の水
- 「神子の水」は遊佐町の女鹿集落にある湧き水を利用した洗い場です。原泉は集落の東側の山にあり、「神泉の水」は湧水を山の神より普請して引いてきたことからこの名がついたと言われています。 洗い場は利用用途...

- 鳥海山大物忌神社 (吹浦口ノ宮)
- 出羽国一ノ宮である鳥海山大物忌神社の起源は大変古く、昭和38年(1963)に1400年祭が執り行われたことから庄内地方では最古の歴史を持つ神社ではないかといわれています。本社は鳥海山の山頂に鎮座し、麓...

- 鳥海山大物忌神社 (蕨岡口ノ宮)
- 出羽国一ノ宮である鳥海山大物忌神社の起源は大変古く、昭和38年(1963)に1400年祭が執り行われたことから庄内地方では最古の歴史を持つ神社ではないかといわれています。本社は鳥海山の山頂に鎮座し、麓...

- 庄内砂丘
- 川から運ばれてきた砂が、大陸からの季節風と波によって陸側に吹き飛ばされてできた砂丘で、南北約35㎞に及びます。約8000年前から成長を始めたこの砂丘では、飛砂を防ぐために、江戸時代(17世紀)からクロ...

- 城輪柵跡
- 国指定史跡。一辺約720mのほぼ正方形の古代城の遺跡で、平安時代(9世紀頃)にこの地域にあった国府*の跡とされています。津波や河川の氾濫の危機にさらされたという記録も残っています。 ※中央から国司が派...

- 勝浦港と北前船文化
- 河口の港だった酒田が西廻り航路の起点として大いに栄えた理由のひとつに外港として機能した飛島の存在があげられます。固い流紋岩でできた館岩が天然の良港となる地形をつくり、多い年には年間500隻を超える北前...

- 奈曽の白滝と金峰神社
- 奈曽の白滝は落差26m・幅11mの名瀑で、滝をつくる岩盤は約10万年以前の鳥海山の溶岩と推定されます。鳥海山の修験の拠点であった金峰神社の境内をすすみ、長い石段を降りると、右手に神社社殿、左手に滝を見...

- 森子大物忌神社
- 鳥海山信仰における滝沢修験の拠点で秋田杉に囲まれた境内は、修験の聖地としての雰囲気に満ちています。 近年、毎年4月第3日曜日に行われている例大祭は、 米俵10俵分(約600kg)と言われる御輿を担ぎ...

- 由利原高原
- 鳥海山の巨大な岩なだれ堆積地が長い時間をかけてなだらかな地形が広がる高原になりました。広大な採草放牧地を活かして秋田由利牛やジャージー牛などが飼育されています。

- 由利原油ガス田
- 石油や天然ガスは、昔湖底や海底にたまった植物が長い時間をかけて分解されてできたものとされています。 かつて秋田県では、特定の時代の地層でしか石油は発掘されないといわれていましたが、由利原台地に油田・...

- 木境大物忌神社
- 木境大物忌神社は、鳥海山信仰の中心だった矢島の修験衆徒の活動拠点でした。 木境周辺では、大物忌神社を中心に春の入峰、虫除け祭り、秋の入峰などのさまざまな修行や行事が、一年を通じて行われていました。この...

- 院内油田跡地
- 院内油田はかつては国内有数の産油量を誇った油田です。 大正11年、大日本石油鉱業(株)が試掘を始めたのを皮切りに、急速な開発が進むことになりました。周辺には、院内・桂坂・小滝・上浜の四油田がありました...

- 仁賀保高原
- 鳥海山の岩なだれ堆積物がつくった標高約500mにある高原部です。爽やかな風を感じながら、広々とした牧草地や緑のなかに点在する湖沼、鳥海山を望むことができる場所です。

- 上郷の温水路群
- 稲作に利用していた鳥海山の冷水を温め、生育障害を解消するため、上郷地区の住民が考案して作った農業用水路です。水路の幅を広く、水深を浅くし、多くの落差を設けて空気と混ぜる構造で、昭和2年に日本で初めて作...

- 由利海岸波除石垣
- 江戸時代に日本海の波浪や強風による塩害から農地と農作物、海岸沿いを走る北国街道を守るために築かれた石垣です。表面は30~50cmの自然石・内部は砂利という構造や、水抜きの配置など、先人の知恵が随所に見...

- 唐戸石
- 「唐戸石」は今からおよそ2,500年前(紀元前466年)に発生した鳥海山の山体崩壊によって山頂付近から大量に流れてきた岩石の一つです。象潟海岸にたくさんある岩の中でも、ひときわ目立った大岩で、高さ4....

- 福田の泉
- 福田の泉は高さ50mほどの崖の下から出る湧き水です。この崖は約14万年前に鳥海山から流れ出た溶岩で、うすい板が積み重なったような板状節理(溶岩がゆっくり流れるときにできる板状の割れ目)が見られます。 ...

- 奈曽の白滝と金峰神社
- 奈曽の白滝は落差26m・幅11mの名瀑で、滝をつくる岩盤は約10万年以前の鳥海山の溶岩と推定されます。鳥海山の修験の拠点であった金峰神社の境内をすすみ、長い石段を降りると、右手に神社社殿、左手に滝を見...

- 白井新田の学田と堰
- 庄内藩の郡代であった白井矢太夫の藩校致道館の学田構想に基づき、1800年より開発された農地です。 鳥海山の冷たい湧水を温めるために水路を何度も迂回させたり、防風樹を植栽するなど数々の知恵がみられます...

- 十六羅漢岩
- およそ10万年前に流れ出て溶岩にいくつもの羅漢像が彫られています。明治の初め、吹浦海禅寺の第21代寛海和尚が、海難事故でなくなった漁師たちの供養と海上安全を願って彫ったものだと伝わっています。

- 神泉の水
- 「神子の水」は遊佐町の女鹿集落にある湧き水を利用した洗い場です。原泉は集落の東側の山にあり、「神泉の水」は湧水を山の神より普請して引いてきたことからこの名がついたと言われています。 洗い場は利用用途...

- 鳥海山大物忌神社 (吹浦口ノ宮)
- 出羽国一ノ宮である鳥海山大物忌神社の起源は大変古く、昭和38年(1963)に1400年祭が執り行われたことから庄内地方では最古の歴史を持つ神社ではないかといわれています。本社は鳥海山の山頂に鎮座し、麓...

- 鳥海山大物忌神社 (蕨岡口ノ宮)
- 出羽国一ノ宮である鳥海山大物忌神社の起源は大変古く、昭和38年(1963)に1400年祭が執り行われたことから庄内地方では最古の歴史を持つ神社ではないかといわれています。本社は鳥海山の山頂に鎮座し、麓...

- 庄内砂丘
- 川から運ばれてきた砂が、大陸からの季節風と波によって陸側に吹き飛ばされてできた砂丘で、南北約35㎞に及びます。約8000年前から成長を始めたこの砂丘では、飛砂を防ぐために、江戸時代(17世紀)からクロ...