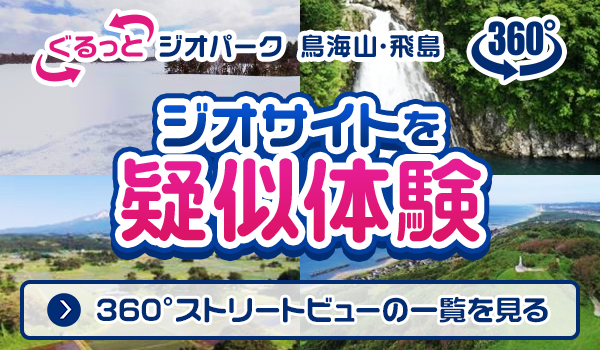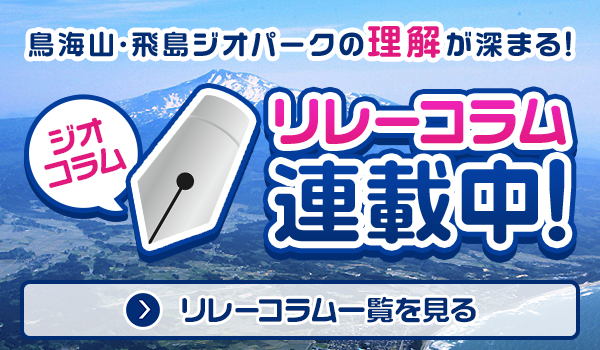観光地一覧
観光地一覧
全て
地質サイト
自然サイト
文化サイト
ビューポイント
施設

- ゴトロ浜
- 南灯台のある崖は高さが20mあり、直径が5~10cmの緑色の丸い石を含む地層と火山灰の地層が交互に積み重なった互層になっています。これはおよそ1650万年前から900万年の間に、海底の火山活動で噴火が...

- 烏帽子群島
- 飛島の西方約1kmにある烏帽子群島は、日本海が広がってきたころに海底火山の活動によって噴出した溶岩が、ゆっくりと冷えて固まるときにできる柱のような節理の柱状節理がたくさん見られる島々です。岩が黒っぽく...

- 御積島
- 御積島は飛島の西方約1kmに位置し、飛島本島よりも高い標高72mあります。日本海が拡大したころの海底での火山活動による流紋岩でできていて、それが隆起してできた島です。 鳥海国定公園の特別保護地区に指...

- 荒崎海岸
- 飛島は日本海が広がってきたころに海底火山から噴き出した噴出物が海底に積み重なり、それが隆起してできた島ですが、荒崎海岸はその噴火の時の軽石や流紋岩の破片を含んだ火山礫凝灰岩でできています。 荒崎周辺...

- 飛島の津波堆積物
- 飛島の西側や北側の法木地区の隆起ベンチを覆っている緩斜面に、有機質の土壌層の中に礫の層が挟まれているところが何か所か見つかります。その露頭は標高5~8mの高さで、堆積物の厚さは合計で1m程度です。 ...

- 八幡崎
- 八幡崎は飛島の北端に突き出た崖で、海底火山の活動による火山灰が堆積したものです。 周りには「ゴジラのしっぽ」や「龍の背」と呼ばれている「岩脈」がたくさん見つかりますが、この岩脈をそれぞれたどっていくと...

- 二俣島
- 二俣島は島全体が玄武岩の「柱状節理」でできています。 日本が大陸から分かれてきて日本海ができたころに、海底火山の活動でできたと考えられていますが日本海が広く大きくなってくる中で、海底火山の活動がたい...

- 巨木の森
- 飛島の気候は対馬暖流の影響を受けるために温暖で、島内には幹廻り4メートルを超えるタブノキやアカマツの巨木が見られます。「巨木の森」には歩道が整備され、よく晴れた日には、鼻戸崎からは海に浮かんだ鳥海山を...

- 勝浦港と北前船文化
- 河口の港だった酒田が西廻り航路の起点として大いに栄えた理由のひとつに外港として機能した飛島の存在があげられます。固い流紋岩でできた館岩が天然の良港となる地形をつくり、多い年には年間500隻を超える北前...

- 八幡崎と西海岸の眺望
- 飛島北端の展望スポット「渚の鐘」から西海岸を望むと、波の侵食によってできた浅瀬(海食台)や海岸段丘などの眺望が広がります。これは飛島が隆起しながら海に削られることでできた地形です。島の周囲は海食台の浅...

- とびしまマリンプラザ
- 飛島の観光拠点で、外観はスルメイカをイメージしたもので、館内には定期船の乗船券売り場、食事処などがあります。 階段の踊り場にはバードウオッチング情報板などがあるので、ぜひご覧ください。 3階からは勝...

- 柏木山と海岸遊歩道
- 柏木山、百合島、舘岩は赤っぽい色をしていて、約900万年前に噴き出した粘り気の強い溶岩が固まった流紋岩でできています。 島の南端から賽の河原にかけては、溶岩が固まるときに流れたきれいな流理構造の見ら...

- ゴトロ浜
- 南灯台のある崖は高さが20mあり、直径が5~10cmの緑色の丸い石を含む地層と火山灰の地層が交互に積み重なった互層になっています。これはおよそ1650万年前から900万年の間に、海底の火山活動で噴火が...

- 烏帽子群島
- 飛島の西方約1kmにある烏帽子群島は、日本海が広がってきたころに海底火山の活動によって噴出した溶岩が、ゆっくりと冷えて固まるときにできる柱のような節理の柱状節理がたくさん見られる島々です。岩が黒っぽく...

- 御積島
- 御積島は飛島の西方約1kmに位置し、飛島本島よりも高い標高72mあります。日本海が拡大したころの海底での火山活動による流紋岩でできていて、それが隆起してできた島です。 鳥海国定公園の特別保護地区に指...

- 荒崎海岸
- 飛島は日本海が広がってきたころに海底火山から噴き出した噴出物が海底に積み重なり、それが隆起してできた島ですが、荒崎海岸はその噴火の時の軽石や流紋岩の破片を含んだ火山礫凝灰岩でできています。 荒崎周辺...

- 飛島の津波堆積物
- 飛島の西側や北側の法木地区の隆起ベンチを覆っている緩斜面に、有機質の土壌層の中に礫の層が挟まれているところが何か所か見つかります。その露頭は標高5~8mの高さで、堆積物の厚さは合計で1m程度です。 ...

- 八幡崎
- 八幡崎は飛島の北端に突き出た崖で、海底火山の活動による火山灰が堆積したものです。 周りには「ゴジラのしっぽ」や「龍の背」と呼ばれている「岩脈」がたくさん見つかりますが、この岩脈をそれぞれたどっていくと...

- 二俣島
- 二俣島は島全体が玄武岩の「柱状節理」でできています。 日本が大陸から分かれてきて日本海ができたころに、海底火山の活動でできたと考えられていますが日本海が広く大きくなってくる中で、海底火山の活動がたい...

- 柏木山と海岸遊歩道
- 柏木山、百合島、舘岩は赤っぽい色をしていて、約900万年前に噴き出した粘り気の強い溶岩が固まった流紋岩でできています。 島の南端から賽の河原にかけては、溶岩が固まるときに流れたきれいな流理構造の見ら...